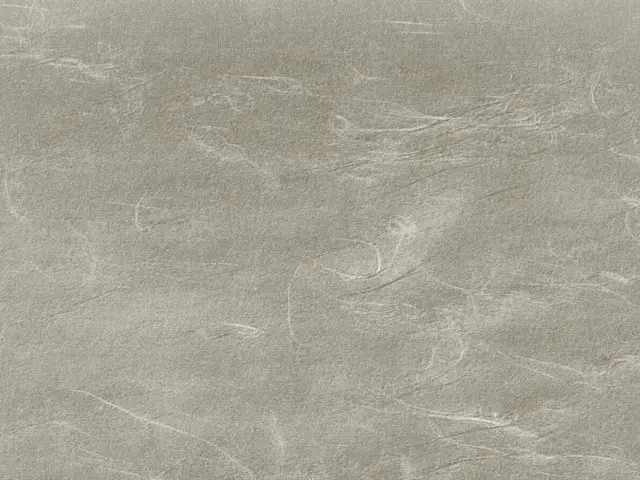壁紙や障子紙、吸音パネルなどに使用される伝統的かつ軽量な建材です。通気性・吸湿性に優れ、和の風合いを演出するのに適しています。破れやすさや耐水性の低さが欠点ですが、加工やラミネートで補うことができます。近年では再生紙を用いたエコ建材も増えています。
| 名称 | 紙 |
|---|---|
| 大分類 | 繊維・布・紙系 |
| 小分類 | 天然繊維 |
| 特徴 | 木材パルプや和紙原料(楮・三椏・麻など)を繊維状にして抄造した天然素材のシート材。加工紙や合成紙も含め用途は多様 |
| 肌目 | 表面は柔らかくマットな質感で、繊維の風合いが感じられる。和紙は特に温かみ・透け感・独特の手触りが特徴 |
| 用途 | 壁紙(和紙クロス)、ふすま紙、照明カバー、障子紙、吸音パネル、断熱紙、装飾用内装材など。調湿性・通気性・意匠性に優れる |
| 産地・メーカー | 国内では岐阜県美濃市(美濃和紙)、島根県浜田市(石州和紙)、高知県(土佐和紙)などが伝統的な産地。建材用には加工紙(合成樹脂含有)も利用される |
紙の概要・特徴
建築材料としての「紙」は、ノートなどに使われる紙そのものではなく、特殊な加工を施した製品を指します。主に、壁の仕上げ材である「壁紙(紙クロス)」と、断熱材である「セルロースファイバー」という二つの使われ方があります。
- 壁紙(紙クロス):パルプを主原料とした自然素材の壁紙です。ビニルクロスにはない、紙ならではの柔らかくマットな質感が特徴です。空気をよく通すため、壁が呼吸するような状態を作り、結露の発生を抑える効果があります。
- 断熱材(セルロースファイバー):新聞古紙などをリサイクルして作られる、綿状の断熱材です。紙の繊維が持つ多くの空気層が熱の伝わりを抑え、高い断熱性能を発揮します。また、木質繊維の特性として、優れた調湿性や吸音性も併せ持っています。
紙のメリットとデメリット
メリット
- 【紙クロス】自然な風合い:ビニルクロスにはない、温かみのある上品な質感が、落ち着いた空間を演出します。
- 【断熱材】高い断熱・気密性:セルロースファイバーは、壁の中に隙間なく吹き込むことができるため、非常に高い断熱性と気密性を確保できます。
- 【共通】優れた調湿性:紙が持つ性質として、湿気を吸ったり吐いたりする力があり、室内の湿度を快適に保つ手助けをします。
- 【共通】環境性能が高い:紙クロスは再生可能な木材パルプから、セルロースファイバーは新聞古紙から作られるため、環境負荷の少ないサステナブルな素材です。
デメリット
- 【紙クロス】汚れに弱く、掃除がしにくい:表面に防水加工がないため、汚れが付着しやすく、水拭きすると破れたり毛羽立ったりする可能性があります。
- 【断熱材】水濡れに弱い:セルロースファイバーは、大量の水に濡れると断熱性能が著しく低下し、乾きにくいという弱点があります。
- 【共通】コストが高い:一般的なビニルクロスやグラスウールに比べて、材料費も専門的な施工費も高価になります。
- 【共通】施工に専門技術が必要:紙クロスは薄く破れやすいため、職人の高い技術が求められます。セルロースファイバーも、適切な密度で吹き込むための専門の機械と技術が必要です。
紙の用途
紙は、その特性に応じて、仕上げ材と機能材という二つの異なる役割で使われます。
- 壁紙として(紙クロス):リビングや寝室、書斎など、落ち着いた雰囲気にしたい部屋や、自然素材にこだわりたい空間の壁・天井の仕上げ材として。
- 断熱材として(セルロースファイバー):住宅の壁の中、屋根裏、床下などに吹き込み、または敷き詰めて使用する断熱・調湿・吸音材として。
- 建具の面材として(襖・障子):日本の伝統的な建具である襖(ふすま)や障子(しょうじ)は、まさに紙を建材として活用した代表例です。