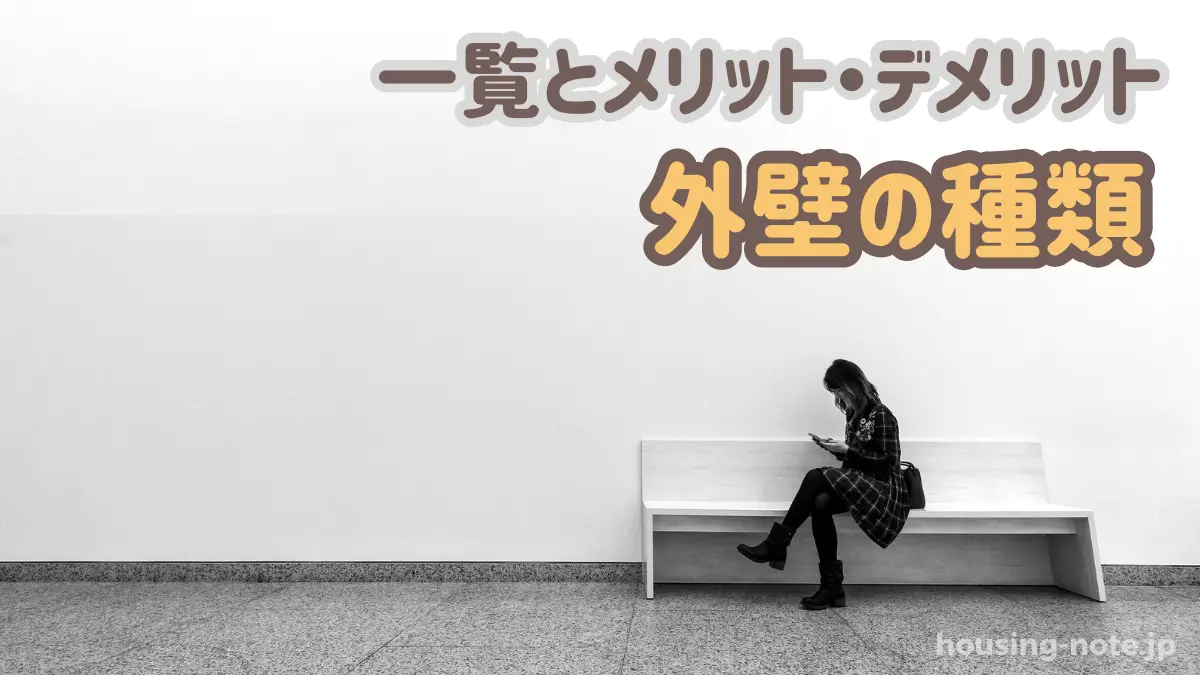家の外観を左右する「外壁」はサイディングとも呼ばれ、単なるデザインの要素だけでなく、家を守る重要な機能を持っています。
外壁材にはさまざまな種類があり、どれがいいか正直わかりません。でも、それぞれの外壁材にも特徴やメリット、デメリットがあります。
どの外壁材を選ぶべきか迷う方のために、この記事では外壁材ごとの特徴を詳しく解説し、選び方のポイントについても紹介します。
外壁の種類を選ぶ前に知っておくべき外壁の役割と選ぶポイント
外壁は住宅を雨風から守るだけでなく、断熱性や耐久性、メンテナンス性にも大きく影響します。
まず、外壁の役割や選び方の基準について解説します。
外壁の役割とは?デザインだけではない重要なポイント

外壁は、家の「見た目」を決める大きな要素であると同時に、次のような機能を果たします。
- 遮熱・断熱:屋外の気温の影響を抑え、室内の快適さを保つ。
- 防水性:雨水が建物内部に侵入するのを防ぐ。
- 耐久性:風雨や紫外線による劣化から家を守る。
- 防火性:火災時に延焼を防ぎ、安全性を高める。
外壁は住まいの第一印象となると同時に「第一防衛線」と言えます。
さらには地域の気候や建物の構造にも適した外壁材を選ぶことが重要であり、機能を無視すると快適な家づくりはできません。
外壁選びで失敗しないための3つのポイント
外壁材を選ぶ際に失敗しないために考慮すべき基準は、以下の3つです。
- 耐久性とメンテナンス性:長く使える素材で、手間がかからないものを選ぶ。
- デザイン性:家全体の雰囲気や好みに合わせて選ぶ。家全体のデザインや周りの環境と調和する外壁材を選ぶことが重要です。
- コスト:初期費用だけでなく、メンテナンスやリフォームといった長期的なコストも検討する。
家を建てる時の価格が「安いから」といって、メンテナンス費用がかさむ外壁材を選ぶと、長期的には高くつく場合があります。
さらには地域的な特性も合わせて考える必要があります。
- 雪国では耐雪性や防寒性が重要
- 海沿いでは錆びにくい素材を選ぶ
これらの条件を無視すると、本来持っている外壁材の機能を損ない、こんなはずではなかったとなりかねません。
外壁の種類一覧|それぞれの特徴とメリット・デメリット
現在の住宅で一般的に用いられる外壁の材料の種類と、これらの材質について、簡単にメリット・デメリットをまとめたものが次の表です。
| 外壁素材 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 窯業系サイディング | デザインの多様性が豊富 コストパフォーマンスが高い 耐火性・耐震性が優れている 施工が容易 | メンテナンス頻度が高い 蓄熱性が高く夏場に室内が暑くなりやすい 防水性能が低く塗装やコーキングが必須 |
| 金属系サイディング | 高い防水性と耐久性、優れた耐震性(軽量) 長期的に経済的 シンプルでモダンなデザイン | 初期費用が窯業系より高い 錆びやすい(塩害地域や塗装剥がれに注意) 傷つきやすい デザインの選択肢が少なく倉庫のような印象を与える可能性 |
| 塗り壁 | 個性的なデザイン性 高い防火性 調湿効果があり快適な住環境を提供 | 高い施工コスト メンテナンスが難しい(汚れやすい、清掃が制限される) ひび割れが発生しやすい 職人の技術による品質差 |
| 木材(板張り) | 温かみのあるデザイン 修理が比較的簡単 高い断熱性と調湿性 自然素材ならではの個性 | 高コストで技術が必要 経年劣化が大きい(変色、変形、虫害) 環境に対する脆弱性(雨や紫外線による劣化) |
| タイル | 高級感とデザイン性 優れた耐久性 低メンテナンスコスト | 初期費用が高い 職人の腕に依存する 重量が耐震性に悪影響 目地材やシーリング材の劣化によるメンテナンスが必要 |
| ALCコンクリート | 軽量で建物の負担が少ない 高い断熱性と遮音性 耐火性に優れる 適切なメンテナンスで50年以上使用可能 | 高い吸水性があり塗装が必須 初期費用が高い 目地が多く劣化リスクが高い メンテナンスを怠ると劣化症状が発生 |
それでは、ひとつずつ外壁の種類と特徴について解説していきましょう!
窯業系サイディングの特徴とメリット・デメリット

窯業(ようぎょう)系サイディングは、日本の住宅で最も一般的に使われている外壁材の一つです。
セメントに繊維質や増量剤を混ぜ、板状に成形し、高温で焼成することで作られます。窯で焼くという過程を経ることから「窯業系」と呼ばれています。
さまざまなデザインや色が選べる点が特徴です。
窯業系サイディングのメリット
窯業系サイディングは、以下のようなメリットがあります。
- 圧倒的なデザインの多様性
-
レンガ調やタイル調など、豊富なデザインと色のバリエーションがあり、好みに合わせて選べます。デザインの選択肢の多さは他の材質と比べても圧倒的で、他にはない個性を出すのにぴったりです。
- 高いコストパフォーマンス
-
パネルは材料費自体も安く、大量生産が可能です。そのため、他の外壁材に比べて価格が安く、初期費用を抑えられます。
- 耐火性と耐震性
-
“焼いて作る”という特性上、耐火性能が高いと言う特徴があります。また、固く軽いため、耐震性が高く建物の安全性を向上させます。
- 施工が容易
-
工場で成型された素材を使用するため、施工が簡単で工期が短縮されます。
窯業系サイディングは、都市部の戸建て住宅や郊外のファミリー向け住宅など、幅広い場面で使われています。
窯業系サイディングのデメリット
では、デメリットにはどのようなものがあるでしょうか?
- メンテナンス頻度が高い
-
定期的な塗装やコーキングのメンテナンスが必要です。表面の塗装は10~15年程度で劣化し、再塗装が必要で放置すると劣化が進みます。
- 蓄熱性が高い
-
セメント素材が熱を吸収しやすく、特に夏場は室内温度が上昇しやすくなります。遮熱効果のある塗料を使用し、室内温度の上昇を防ぐのが有効な対策です。
- 防水性能が低い
-
素材自体に防水性能がないため、塗装による防水処理が必須です。また、パネルの継ぎ目は防水のためのコーキングが必要で、コーキングの劣化に対してもメンテナンスが必要です。
窯業系サイディングを選択する場合、10〜15年ごとに必要となるメンテナンス費用も考慮して、あとあと「お金が想定外にかかった」と後悔しないように計画しましょう。
▼ さらに詳しく
金属系サイディングの特徴とメリット・デメリット

金属系サイディングは、トタンやガルバリウム鋼板、SGL鋼板、またはアルミなどがあります。
昔はトタンがよく使われていましたが、住まいづくりに関して、現在ではガルバリウム鋼板、SGL鋼板などが主流です。
▼ さらに詳しく
金属系サイディングのメリット
金属サイディングには以下のようなメリットがあります。
- 高い防水性と耐久性
-
金属素材のため、水を通しにくく、高い防水性を持っています。また、セメント系外壁材と異なり、ひび割れのリスクが低く、耐用年数も約30年〜40年と長めです。気温や日射による変形も少なく、劣化の少なさにいい影響を与えます。
- 優れた耐震性
-
金属系サイディングは、重たい金属でできているので重いイメージを持たれがちですが、厚みが1mmよりもずっと薄く、窯業系サイディングと比べて約3分の1の重さしかありません。そのため、建物への負荷が少なく、地震の影響を受けにくい特性があります。また、軽量であるため施工も容易です。
- コストパフォーマンスの良さ
-
軽量で加工・施工が容易なため、工事費を抑えられます。また、長寿命であることから、長期的に見て経済的です。
金属サイディングは耐久性、や長期的なコストパフォーマンスを求める人にとって、魅力的です。
また、デザイン面では、シンプルかつモダンで近代的なデザインから人気の外壁材と言えます。
金属系サイディングのデメリット
- 価格
-
コストパフォーマンスが良いと言っても、窯業系サイディングと比べて価格が割高です。新築時では窯業サイディングの約1.3倍程度の値段となります。さらにリフォームで金属系サイディングに変更する場合では、外壁塗装によるメンテナンスに比べると2倍以上のコストがかかります。
- 錆びる素材である
-
金属素材のため、環境によっては錆びが発生する可能性があります。特に塗装が剥がれた場合や海が近い塩害地域、雨の多い地域では注意が必要です。特に鋼板を構造材に固定するビスが外に露出しているタイプは、ビス止め箇所から錆が生じることが少なくありません。
- 傷つきやすい
-
薄い金属でできているので、鋭利な物や飛び石、ものをぶつけたりすると傷ついたりへこんだりしやすいデメリットがあります。さらに傷により塗膜や表面のメッキ層が剥がれると錆びの原因となる可能性があります。
- 外観のデザインが制限される
-
選べるデザインやカラーが、窯業系サイディングと比べて少なく、外観のバリエーションが限られてしまいます。また見る人によっては、倉庫のように感じる人もいます。デザインをミスすると、さらに倉庫感が出てしまっておしゃれとは程遠いデザインになりかねません。
また、耐久性が高いからと言ってメンテナンスが必要ないというわけではありません。適切な使用とメンテナンスで、その寿命を延ばすことができます。
▼ 関連記事
塗り壁(モルタル、漆喰など)

塗り壁は、家全体を滑らかに覆う仕上げ方法で、職人の技術による独自の風合いが魅力です。モルタルや漆喰などが代表的で、伝統的な日本家屋や現代建築のデザインにも幅広く採用されています。
天然素材を主成分とし、ナチュラルで継ぎ目のない平らな仕上がりが可能となりますし、職人の手作業による多様な表情や風合いを演出できるという特徴があります。
塗り壁と食う裕の 独特のテクスチャーや立体感のある仕上がりは、 和風からモダンなデザインまで幅広く対応可能できる材質です。
塗り壁のメリット
塗り壁のメリットには、以下のような点があります。
- 個性的なデザイン性
-
塗り壁は手作業で施工されるため、既製品では得られないオリジナルなデザインを実現できます。塗り方ひとつでもその見た目を変化させることができ、その見た目の雰囲気が変わります。また自然な風合いなので、個性があるのだけど万人受けするデザインに仕上げられます。
- 高い防火性
-
モルタルや漆喰は燃えにくい素材であり、外壁として使用することで防火性能が向上します。特に木造住宅においては、耐火性が重要な要素となります。
- 高い耐久性
-
漆喰は時間と共に強度が増し、その耐用年数は100年以上とも言われています。モルタルも適切なメンテナンスを行うことで、30年程度の耐久性を持ちます。
- 調湿効果がある
-
漆喰の壁材は多孔質であり、湿気を吸収・放出する特性があります。これにより、室内の湿度を調整しやすく、快適な住環境を提供します
塗り壁はデザイン性や機能性を重視する住宅に適した選択肢と言えます。
塗り壁のデメリット
- 高いコスト
-
塗り壁は基本的に職人の手作業で施工します。住宅の壁という広い範囲を施工するので、時間と労力がかかります。材料費も高い傾向がありますので、その結果、施工費が高くなるのはまぬがれません。
- メンテナンスが難しい
-
塗り壁は表面がざらざらしている砂や泥はね、苔、藻、カビなどの汚れが付きやすく、きれいな外観に保つためには定期的な清掃が必要です。しかし、高圧洗浄機などを使うと壁材が剥がれてしまう危険がありますので使用は避けた方がよく、適切な清掃方法が限られます。
- ひび割れのリスクがある
-
乾燥過程や建物の振動によってひび割れが発生しやすいです。引き渡し前であれば施工不良でやり直しもさせやすいですが、数年経過した後であったり、地震などで発生したひび割れは保証の対象外となるため、修繕費用が掛かってしまいます。特に漆喰は傷つきやすい性質があります。
- 職人の腕によって品質に差が出る
-
仕上がりの美しさや耐久性が職人の技術に大きく依存します。また、高い技術を持った職人さんには高齢の方も多く、ハウスメーカー側が人の確保に苦労することも少なくありません。
塗り壁はデザイン面でも質感の面でも上質で素晴らしい材料ですが、取り扱いが難しい面があります。これらのデメリットを考慮し、メンテナンス計画や予算を立てる必要があります。
木材(板張りや羽目板など)

木材の外壁材は、自然素材ならではの温かみと独特の風合いが特徴です。無垢材特有の外観と、時間が経つごとに表情を変える変化が楽しめます。また、環境負荷も少ない再生資源です。
木材を外壁材に使用した際の、主なメリット・デメリットは以下の通りです。
木材外壁のメリット
木材の外壁材には多くのメリットがあります。以下に主なメリットをまとめます。
- 温かみのある独特なデザイン
-
一般的な住宅にはない温かみのある、万人受けするデザインが魅力です。他の材質は無機質な見た目になりがちですが、木の風合いが織りなす独特の雰囲気は唯一無二です。
- 修理が比較的簡単
-
壁材に損傷が生じたとき、木材の壁は部分的な張り替えが比較的簡単にできます。
- 個性的な外観が作りやすい
-
自然素材ですので、木目の模様は千差万別、唯一無二の個性を作りだすことができます、
- 高い断熱性と調湿性
-
木材は内部にたくさんの気泡を持っているため、断熱性が高く、夏は涼しく冬は暖かい室内環境を実現できます。また、湿度が高いときは木が湿気を吸込み、乾燥していると気には逆に放出して、湿度の調整ができます。なので、快適な環境が維持できやすい材料です。
木材外壁のデメリット
木材の外壁材には以下のようなデメリットがあります。
- 施工に技術が必要で高コスト
-
品質のばらついた材料を扱いますので、施工に高度な技術が必要となります。そのため、出来上がりの品質も施工会社や担当した大工によって異なる可能性が考えられます。材料の価格もさることながら、施工費用の面でも割高になる傾向があります
- 経年劣化が大きい
-
木材は経年による変色や変形のリスクが高い材料です。乾燥しすぎると割れてしまったり、虫食いが発生する可能性もあります。その都度修繕をしていかないとすぐに劣化して行きます。
- 環境への脆弱性
-
雨・雪や紫外線による劣化が起こりやすく、定期的な修繕や薬剤の塗り直しなど、定期的なメンテナンスが必要。
木材の外壁材を選ぶ際は、適切な材料選択と施工方法、そして設計上の配慮が重要です。また、建築する場所によっては建築基準法上の制限があり、防火認定を受けた材料を使用する必要がある場合もあります。
タイル

タイルの外壁材は、高温で焼き固めた石や粘土、レンガといった無機質素材で作られています。
タイル外壁は、耐久性の高さとメンテナンスのしやすさから、長期間美しい外観を保つことができる素材です。特に高級住宅や都市型住宅でよく採用されています。
タイルのメリット
タイル外壁には、3つの主なメリットがあります。
- 高級感とデザイン性
-
表面の質感や素材の違いにより、多様な外観を実現できます。色々な素材を組み合わせたり、異なる色・素材の組み合わせで、高級感のある個性的な外観が実現できます。
- 高い耐久性
-
タイルは紫外線や風雨の影響を受けにくく高い耐久性、対候性そして傷にも強い素材です。そのため、いつまでもきれいな外観を保つことができます。
- 低メンテナンスコスト
-
耐久性の高さのメリットとして、他の外壁材と比較して、メンテナンス費用が約4割に抑えられます。汚れにくく、長期的な維持管理が容易です。
タイル外壁は住宅の外観に高級感と耐久性をもたらす魅力的な選択肢です。
タイルのデメリット
一方で、タイル外壁のデメリットは次のようなものがあります。
- 初期費用が高い
-
他の外壁材と比較して、初期費用が高くなります。材料費も他の素材に比べると価格なりますし、職人が下地造りから仕上げまで手作業で仕上げていきますので、建築費はどうしても高くなりがちです。
- 施工の品質が職人の腕に依存
-
仕上がりの品質は職人の腕によって大きく左右されます。適切に施工されないと、耐久性や外観に影響を与える可能性があります。施工不良や経年劣化により、タイルが剥がれ落ちる可能性もあります。信頼できる施工業者にお願いしたいですね。
- 素材が重く耐震性に悪影響
-
タイルはその素材自体が重いので、地震による揺れが起こった時に構造材に加わる力が大きくなり、悪影響となります。木造住宅の場合、タイルの重さに耐えられる構造が必要です。特に古い建物や施工が不適切な場合、振動でタイルが落下するリスクがあります。
- メンテナンスフリーではない
-
タイル自体は耐久性が高いですが、目地材やシーリング材の劣化に注意が必要です。部分的な補修や交換が難しい場合もあります。
定期的な点検を行い、早期対応がメンテナンス費用を抑えるために大切です。
ALCコンクリート
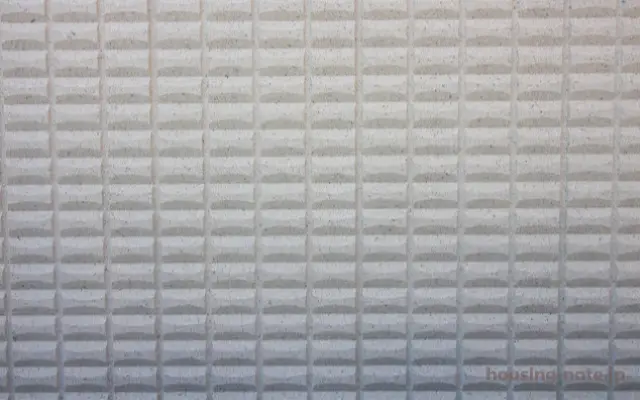
ALC(Autoclaved Lightweight Concrete;軽量気泡コンクリート)は、軽量かつ耐久性が高い外壁材で、耐火性や断熱性に優れている点が特徴です。
日本では旭化成ホームズのへーベル板が有名ですが、他のハウスメーカーでも採用されていたり、旭化成ホームズで建てなくてもへーベル板を使用できることもあります。
ALCコンクリートのメリット
ALCコンクリートには以下のようなメリットがあります。
- 軽量である
-
普通のコンクリートの約4分の1の重さで、建物全体の軽量化に貢献します。壁材が軽いと、地震時の揺れや構造体への負担を軽減することができます。
- 高い断熱性と遮音性
-
内部の無数の細かい気泡が断熱材の役割を果たし、普通コンクリートの約10倍の断熱性能を発揮します。断熱性が高いと空調のランニングコストを抑えることができ、結露防止にも効果があります。また遮音性も高くなります。
- 優れた耐火性
-
不燃材料として認定されており、火災時に有害物質を発生しません。
- 優れた耐久性
-
適切なメンテナンスを行えば、50年以上の長期使用が可能です。
ALCコンクリートは高い性能が求められる現代の家づくりに最適な素材として、欠かせない建材として位置づけられています。
ALCコンクリートのデメリット
万能なように思えるALCコンクリートにも、次のようなデメリットがあります。
- 吸水性が高い
-
ALCパネルの表面には無数の細かい穴があり、非常に水を吸収しやすい構造になっています。このままだと耐久性の低下につながるので、基本的には塗装による防水処理を行う必要があります・可能性があります。定期的な塗り替えやメンテナンスを怠ると、耐久性が著しく低下します。
- 初期費用が高い
-
他の外壁材と比較して製造に手間のかかる高性能な材料であるため、初期の建築費用が高くなる傾向があります。
- 継ぎ目が多く目地の処理部が劣化する
-
ALCコンクリートはパネル構造のため、目地が多くなります。目地が劣化してくると美観を損なう可能性があり、また水の侵入リスクも高まります。そのため定期的なメンテナンスは欠かせません。
適切なメンテナンスを行わないと、チョーキング現象、目地の亀裂、ひび割れ、コケ・カビ・藻の発生、色褪せ、膨れ、剥落・欠損などの劣化症状が現れる可能性があります。
これらのデメリットを考慮し、適切なメンテナンスと管理を行うことが、ALCコンクリートを長期間効果的に使用するために重要です。
外壁素材の見分け方

外壁素材には窯業系サイディング、モルタル、タイル、金属系サイディングなど、さまざまな種類があります。その中でも、窯業系サイディングは技術の進化によって、他の素材と見分けがつきにくくなってきています。
- 1. デザイン技術の進化
-
- 窯業系サイディングは、リアルなテクスチャや模様が施されており、肉眼では天然素材と見分けがつきにくいほど高精度です。
- 特に、3Dプリント技術を応用した模様では、自然素材のような不規則性を表現できます。
- 2. 施工後の視覚的な効果
-
- 窯業系サイディングは外壁全体に統一感を持たせるよう施工されます。一方、天然素材の場合、不規則な模様やサイズの違いがそのまま残ることがあります。
- 遠目から見ると、施工後の統一感が本物の天然素材と見間違える原因になります。
- 3. 似た施工方法
-
- 窯業系サイディングは、タイルや天然石と同様に現場で貼り付けるため、素人目には施工方法自体が似ています。
- また、目地の施工方法も天然素材と似ていることが多いです。
- 4. メンテナンスが目立たない
-
- シーリング材が目地に使われているため、適切にメンテナンスされていると目地が目立たなくます。窯業系サイディングと天然素材の違いを判断しにくくなる原因です。
特に、タイルや天然石、レンガなどと似たデザインが可能なため、外観だけで判断するのが難しい場合も多いです。
そこで、窯業系サイディングを見分けるためのポイントを解説します。
見た目から判断する
窯業系サイディングは、デザインの多様性が魅力の一つです。タイル調、レンガ調、木目調など、幅広いパターンがあり、本物の素材に近い質感を再現できます。しかし、次のポイントに注目することで見分けることが可能です。
- パターンの規則性
-
窯業系サイディングは工場で量産されるため、模様やテクスチャが規則的に繰り返される傾向があります。タイル調やレンガ調の場合、同じデザインが何度も出現するため、近距離で観察すると見分けやすくなります。一方、本物のタイルや天然石は模様が不規則で、一つ一つ異なる個性があります。
- 光の反射
-
窯業系サイディングは表面が塗装されており、光が均一に反射することが特徴です。天然素材は多孔質な場合が多く、光がランダムに反射するため、近くで観察すると質感の違いが分かります。
構造から判断する
窯業系サイディングはボード状のパネルを組み合わせて施工されるため、その構造が他の素材と異なります。以下の点に注意してみましょう。
- 目地の存在
-
窯業系サイディングは、ボード同士を貼り合わせて施工するため、継ぎ目である「目地」が見られます。この目地部分にはシーリング材が充填されており、一定の間隔で継ぎ目が確認できます。一方、タイルやレンガでは、目地は素材を接着するためのものですが、施工の仕方が異なるため見た目にも差があります。
- ボードサイズ
-
一般的な窯業系サイディングのボードサイズは455mm×3,030mmなど規格化されているため、特定の間隔で目地が現れます。この規則性が見分けのヒントになります。
触感から判断する(肌触りや叩いた時の音)
外壁に実際に触れたり叩いたりすることで、素材の違いを感じ取ることができます。
- 肌触り
-
窯業系サイディングの表面は、塗装による仕上げが施されており、滑らかで均一な感触です。対して、天然石やタイルは自然な凹凸があり、触るとその質感を感じることができます。
- 叩いた時の音
-
窯業系サイディングはセメントを主成分とするため、叩くと硬く鈍い音がします。一方、金属系サイディングでは軽い音が響き、タイルや天然石では重厚でしっかりした音がします。この音の違いは、素材ごとの密度や構造に起因します。
まとめ:外壁素材の特性を知って住まいに合った選択を!

外壁材の選択は、住宅のデザインだけでなく、快適性や耐久性、さらには維持費用に大きな影響を与える重要な決定です。本
記事では、主要な外壁材である窯業系サイディング、金属系サイディング、塗り壁、木材、タイル、ALCコンクリートについて、その特徴やメリット・デメリットを詳しく解説しました。
外壁選びで失敗しないためには、以下のポイントを押さえることが大切です。
- 耐久性とメンテナンス性を重視し、長く使える素材を選ぶ。
- 家全体の雰囲気や好みに合わせたデザイン性を考慮する。
- 初期費用と長期的なコストのバランスを検討する。
- 自分の住宅の立地や環境条件に適した素材を選ぶ。
また、外壁材の選択肢が増える一方で、素材ごとの違いを見極める知識も求められます。
この記事を参考に、それぞれの外壁材の特性を理解し、住まいに最適な選択をしてください。正しい外壁材の選択は、快適で長く愛される住まいづくりの第一歩です!